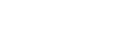あの大きな橋はどうやって作っているんだろう?
地震や洪水が起きたら住んでいるまちや私たちは
だいじょうぶなのかな?
もしかするとあまり気づかないかもしれないけど、
生活の中でとても大切な役割を担っている学問???。

コース・学科目長からのメッセージ
大阪大学の社会基盤工学科目/コースは、数少ない航空工学科が戦後に廃止され、それに代わる学科として戦後の国土復興を担うために1947年に設置されました、土木と建築の両分野を有する構築工学科を前身としています。これ以降、1952年には構築工学科に土木コースと建築コースの2課程が設置されて順次研究室が整備され、1966年に土木工学科・土木工学専攻と建築工学科・建築工学専攻に分離拡充、1970年に土木工学専攻修士課程、1972年に同博士課程が設置、1999年に地球総合工学科土木工学科目・土木工学専攻、2005年に地球総合工学科社会基盤工学科目および地球総合工学専攻社会基盤工学コースとして改組拡充し、発展してきました。
当学科目/コースは、主に社会基盤施設の基礎となる構造物の計画、設計、施工、維持管理の技術を創造する「社会基盤工学講座」と、国土・都市計画、水環境、交通、防災、海岸保全など、社会基盤施設のシステム化を志向する「社会システム学講座」の2講座体制で、専門分野間のバランスに配慮しつつ、特色ある教育と研究に取り組んでいます。大阪大学憲章で謳われている「実学の重視」を特徴とし、"社会基盤=公共"の信念の下、少数精鋭で社会に貢献できる優秀な人材を育て、社会に送り出すことができる私たちの学科目/コースに、皆さんを迎える日が来るのを楽しみに待っています。